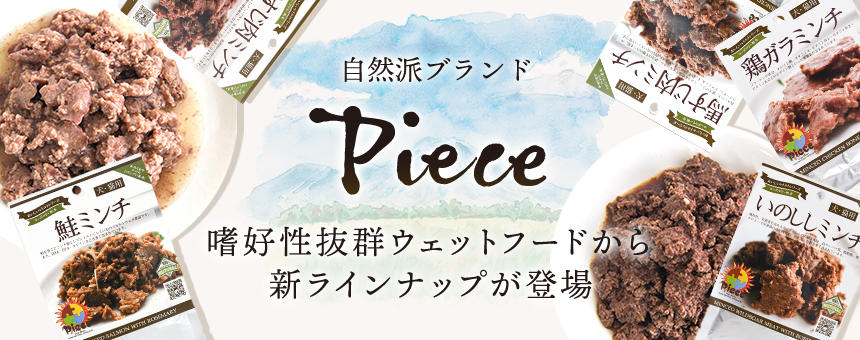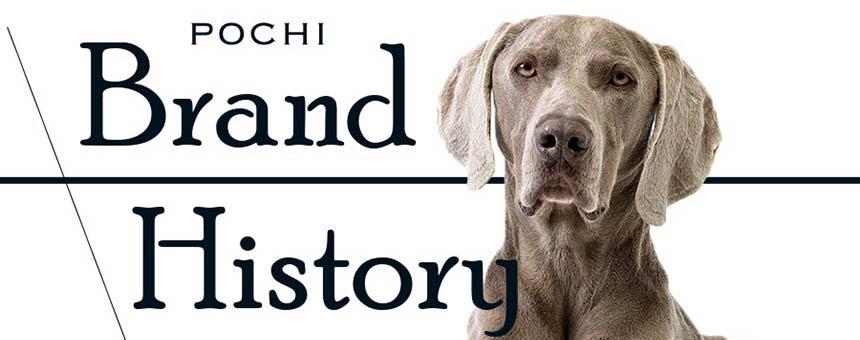- コラム
- 知るという、栄養
2025.06.30
子どもを病院や司法の場で支える、働く犬たちとは?

先入観を持たず、子どもたちの小さな心にすっと入り込む力を持つ犬。その独特の共感性を活かして"付添犬"や"ホスピタル・ファシリティドッグ®"として働く犬たちの存在意義、そして、犬たちだからこそもたらすことができる効果について、そのお仕事の様子とともにご紹介します。(POCHI編集チーム)
今回のお役立ち情報付添犬とホスピタル・ファシリティドッグ®
司法の場で子どもを支える“付添犬”と、こども病院に常勤して入院中の子どもに寄り添ったり子どもと遊んだりする“ホスピタル・ファシリティドッグ®”の活動を紹介します。
司法の場で子どもを支える“付添犬”
2020年に日本で初めて、付添犬が誕生しました。付添犬とは、虐待などの被害を受けた子どもが、自分の受けたできごとについて司法関係者や医療従事者といった他者に、安心して伝えられるように手助けをする犬です。
「心身ともに傷つき閉ざされた子どもの小さな心に、犬はすっと入り込む力を持っていると感じます。入ってきた情報からあれこれ判断しがちな人間と違い、犬はなにも知らず先入観もなく、ただただそばに寄り添える存在です。独特の共感性を持つ犬たちだからこそ、人間にはできない大きな力を子どもに発揮していると実感せずにはいられません」
このように語るのは、認定NPO法人子ども支援センターつなっぐ(以下、つなっぐ)理事で、日本の付添犬の実現に力を尽くしてきた吉田尚子獣医師。

付添犬は包容力のある穏やかな犬で、一般の犬が入ることができない裁判所、検察庁、警察署、児童相談所といった施設でも落ち着いて行動ができ、指示に従うことができます(写真提供:つなっぐ)
日本で唯一、付添犬の派遣をしている団体であるつなっぐの付添犬認証委員会から認証を受けて活動をしている付添犬は、2025年春現在13頭。ゴールデン・レトリーバー、ラブラドール・レトリーバー、スタンダード・プードル、ボロニーズ、チワワ、ビション・フリーゼ、ゴールデン・ドゥードルなど小型犬から大型犬まで多犬種にわたります。
2025年春まで、裁判、検察や警察からの聴取、司法面接時の同席と前後のふれあいで約200件の付添犬活動を実施してきました。

2024年は1年間で44回の付添犬活動が行われました(写真提供:つなっぐ)
子どもに付添犬が必要な理由
付添犬のエピソードは、小学校高学年くらいから大人までが読める『いっしょにいるよ 子どもと裁判に出た犬 フランとハッシュの物語』(涌井学著/小学館)にも多数紹介されていますが、吉田獣医師がとくに印象に残ったできごとをひとつ紹介します。
「『一切話しもせず、犬に会うことも無理だと思います』と言われていたお子さんが以前、付添犬活動の場にやってきました。
『ワンちゃんにだけ会って行く?』と児童精神科医に促されて来たのですが、いざ付添犬とふれあったとたんに表情がやわらぎ、硬く閉ざしていた口を開いて1時間も自分に起きたことを話せたんです」
子どもに関わる専門家も、いい意味で犬の力には裏切られ続けているそうです。

付添犬の書籍に登場する、付添犬第一号のフランちゃん(©Kyone Usui)
「付添犬を触れなかった子どもも、付添犬活動が終わって施設に戻って『今日は犬がいて、いいことがあった』とケースワーカーさんに伝えていたりします。それを聞くと、その空間にただ犬がいるだけで子どもの役に立っているのだと感じることも少なくありません。
犬は自分を必要としている子どものもとへ、まるで吸い込まれるかのように近づいて行きます。それを目にするたびに、犬は私たち人間の力を超えていると実感させられます。付添犬は子どもの命の瀬戸際で子どもに寄り添いながら、犬自身の生命力と相手へのやさしさを伝え、子どもの生きる力をも引き出しているのではないでしょうか」(吉田獣医師)

つなっぐと提携する社会福祉法人日本介助犬協会と公益社団法人日本動物病院協会(JAHA)それぞれで認定を受けた犬とハンドラーが、さらに付添犬認証委員会の認証を受け、内容やニーズに合わせて付添犬活動を行っています(写真提供:つなっぐ)
病院で子どもに寄りそう“ホスピタル・ファシリティドッグ®
子どもを支えるために働いているのは、付添犬だけではありません。
シャイン・オン!キッズの“ホスピタル・ファシリティドッグ®”は、医療チームの一員として特定の病院にハンドラーとともに常勤し、入院治療している子どもたちの心の励みになっています。
「同じ犬が繰り返し多くの時間を子どもと一緒に過ごせば、闘病するうえでの仲間意識を持てて絆が形成されます。それが、小児がんや重い病気の子どもやそのご家族の生活の質の向上に重要だと思っています。ホスピタル・ファシリティドッグ®のサポートによって治療を前向きとらえられ、子どもたちは自尊心を保てるようになると感じています」
取材に訪れた神奈川県立こども医療センターでこのように語るのは、ハンドラーで看護師としての経験も持つ森田優子さん。

神奈川県立こども医療センターにて、森田さんと現ホスピタル・ファシリティドッグ®のアニー(右)とオリ(左)
ホスピタル・ファシリティドッグ®は、毎朝9時に病院に出勤。そこで1時間仕事しては1時間以上休むというスタイルで17時まで、実質合計3時間ほど病棟に通います。
その仕事は、薬が飲めない際や食事がすすまない際の応援、採血や点滴時の応援、手術室への移動の付き添い、痛みを伴う処置の付き添いや、鎮静麻酔導入までの付き添い、リハビリテーションの応援など多岐にわたります。
ふだんはハンドラー宅で暮らし、ホスピタル・ファシリティドッグ®が休日に遊ぶ様子などはインスタグラムで紹介されていて、それを楽しみに見ている子どもたちも多いといいます。

ホスピタル・ファシリティドッグ®はハンドラーと一緒に暮らしながら10歳ごろの引退まで働きます
犬がいるから治療も検査も頑張れる!
森田さんは、2010年にホスピタル・ファシリティドッグ®のベイリーが日本で初めて導入された際のハンドラーでもありました。それから約15年間、医療チームの一員として病院に通い続けてきたなかで、ある小児がんの10歳の子のことが印象に残っているといいます。
「ベイリー時代から会ってたお子さんで、小児がんの再発を繰り返しても治療を毎回頑張っていました。ところが長期入院中の終盤はすべての検査や治療がイヤになってしまって……。けれども、アニーが行くと、しばらく黙ってアニーをなでたのち『検査、やる』と。ベッドでアニーと添い寝しているうちに自分の気持ちを消化して、やると決められたんだと思います。
医療スタッフがそばに寄り添っていたとしても、検査や治療をさせたいという思いを子どもたちが読み取ってしまうこともあるかもしれません。でも、犬は治療をともに頑張ってきた存在で、ただただやさしくそばにいてくれます。そんな犬たちの力は偉大だと感じています」

ホスピタル・ファシリティドッグ®はほとんど毎日、病室のベッドなどで子どもたちに寄り添いながら癒し励ましています
ホスピタル・ファシリティドッグ®がいると、医療スタッフから「おかげで一日中の元気を充電できた、ありがとう」「場の雰囲気がなごんだわ~」と言われたりもするそうです。
病院スタッフが笑顔になれることで患者さんにも好影響がおよぶのは、言うまでもありません。
犬の得意を活かしたゲームを考案しトレーニング
神奈川県立こども医療センターに2025年4月現在勤務する9歳のアニーちゃんは愛嬌があるタイプ、3歳のオリちゃんはマジメな優等生タイプだそうで、それぞれの特技も異なります。
「オリが得意なのは、宝さがしゲームですね。オリのおもちゃを子どもたちに隠してもらって、オリがにおいを頼りに探すゲームで、毎回とても盛り上がります。
ただ『歩きに行こう』と看護師が誘っても、とくに手術直後などは歩こうとしない子どもが多いのですが、犬がいると自分からベッドから離れてくれます。先日も『オリとお散歩に行きたい』とお子さんが自ら言い出し、ご家族もびっくりされていました」(森田さん)

取材中「遊ぼうよ」とおもちゃをくわえて近寄ってきてくれたオリ。2頭の姿を見て筆者も自然と笑顔になりました
病棟やプレイルームでの活動メニューは、ハンドラーが考えます。2歳前後でトレーニングを卒業するまでに犬が覚える合図の基準は、シャイン・オン!キッズでは70個以上。
アニーちゃんはレトリーバーらしくおもちゃを回収し、オリちゃんはおもちゃをかごに入れに行くのを得意としているとのこと。
「ハンドラーは、子どもの成長発達を促したりリハビリにつながるゲームを、犬の特性を活かしながら考えています。得意なことをしながらほめられて、犬たちもうれしそうに働いています」(森田さん)
子どもに寄り添う犬を増やすために
森田さんがベイリーと15年前に静岡県立こども病院でホスピタル・ファシリティドッグ®の活動を始めた当初は、その後、神奈川県立こども医療センター、東京都立小児総合医療センター、国立成育医療研究センターと全国に活動の場が順調に広がっていくことは想像がつかなかったといいます。
「これまではハワイのトレーニングセンターから来た犬が多かったのですが、今は補助犬育成の国際基準と倫理規定に則り、国内での育成を本格的に始めました。
日本全国のこども病院にホスピタル・ファシリティドッグ®を常勤させることを目指して、活動の幅をさらに広げていきます」と、認定NPO法人シャイン・オン・キッズのハンドラー・リーダーでもある森田さんは語ります。

名誉ホスピタル・ファシリティドッグ®のベイリーの横にラブラドール・レトリーバーのオリ、そして自身のパネルの横にはゴールデン・レトリーバーのアニー
付添犬の育成も、つなっぐは力を入れています。2024年3月までに認証された付添犬は、引退犬を含めて21頭。
「日本での付添犬活動は、アメリカでコートハウス・ファシリティ・ドッグの育成に携わってきたCourthouse Dogs® Foundationと連携して歩んできました。アメリカには付添犬(コートハウス・ファシリティ・ドッグ)が約300頭いるので、日本でもその数と活動の場を増やしていきたいと望んでいます」
このように語る吉田獣医師はまた、犬の魅力を社会に広く伝えている一般飼い主と家庭犬の存在も、子ども支える犬たちの活動に貢献していると説きます。
「犬たちが心地よく社会に溶けこんでいることを飼い主さんが日常的に体現してくださるからこそ、犬と暮らしていない人も受け入れやすくなると思うのです。
犬が家族の一員として幸せで、人を信頼しているという土壌がなければ、犬を介在した活動はできません。これからも、人と犬がほほえましくあるウェルビーイングの様子を、社会で伝えていただければうれしいです」

病棟ベッドでの添い寝を好むというオリは、取材中も自然とこの姿勢でウトウト
付添犬やホスピタル・ファシリティドッグ®など、特殊な環境にいる子どもを癒し励ます犬とその活動の場が日本にもっと増えていくことを願ってやみません。
*1 ホスピタル・ファシリティドッグ®は認定NPO法人シャイン・オン・キッズの登録商標です。
■ 文・取材 臼井京音
 ドッグライター・ジャーナリストとして、20年以上にわたり世界の犬事情を取材。現在は犬専門誌『Wan』をはじめ週刊誌、Web媒体、会報誌等で情報発信を行う。以前は『愛犬の友』誌、毎日新聞の連載コラム(2009年終了)などでも執筆。著書に『うみいぬ』『室内犬の気持ちがわかる本-上手な育て方としつけ方をアドバイス!』がある。
ドッグライター・ジャーナリストとして、20年以上にわたり世界の犬事情を取材。現在は犬専門誌『Wan』をはじめ週刊誌、Web媒体、会報誌等で情報発信を行う。以前は『愛犬の友』誌、毎日新聞の連載コラム(2009年終了)などでも執筆。著書に『うみいぬ』『室内犬の気持ちがわかる本-上手な育て方としつけ方をアドバイス!』がある。
現在は元野犬の中型犬と暮らす。歴代愛犬のノーリッチ・テリア2頭と同様にボールを追いかけることが喜びで、趣味はテニスとバレーボールと写真撮影。パリやNYで撮影し自宅暗室で焼いたモノクロ写真は、ドッグリゾートWoof、ペットショップP2などのインテリアにも使用されている。
取材協力:
*1 NPO法人子ども支援センターつなっぐ(寄付等も受け付けています) https://tsunagg.org
*2 シャイン・オン!キッズ(寄付等も受け付けています) https://sokids.org/ja/